キリムとは、古くから世界各地で親しまれてきた伝統的な布の一種です。見た目の美しさだけでなく、長い歴史や深い意味が込められている点が特徴です。この記事では、キリムの歴史、作り方、模様の意味、暮らしへの取り入れ方、お手入れの方法などを、わかりやすくご紹介します。
キリムってなに?どこで生まれたの?

キリムは、トルコ、イラン、中央アジア、北アフリカなどの地域で昔から作られてきた平織りの布です。最も古いものは、約9000年前のトルコ・チャタルホユク遺跡で使われていたという記録があります。
この布は、もともとテントの床に敷いたり、壁に飾ったり、結婚式やお葬式などの大切な場面でも使われていました。長い年月をかけて多くの地域に広がり、それぞれの文化や気候に合わせた模様や色が生まれました。
現在では、ラグやクッションカバー、壁飾りなど、インテリアとしての用途も広がり、おしゃれであたたかみのあるデザインとして人気があります。
キリムの作り方と材料について
キリムは「平織り(ひらおり)」という技法で作られています。たて糸とよこ糸を交互に織り込むことで、表と裏の両方に同じ模様が出るのが特徴です。
この織物は軽くて薄いため、折りたたみや持ち運びがしやすく、使いやすさも魅力のひとつです。模様には三角形やひし形などの幾何学模様のほか、花など自然をモチーフにしたものもあります。
主な材料は羊の毛で、やわらかく丈夫で、染色しやすいという特性があります。そのほかにも綿や絹、ヤギやラクダの毛が使われることもあります。自然由来の草木染めを使ったものは、落ち着いた色合いと時間が経つごとに深まる風合いが楽しめます。
模様に込められた意味や願い
キリムの魅力のひとつが、模様に込められた意味です。たとえば「エリベリンデ(手を腰に当てた女性)」という模様は、母のような優しさや家族への思いやりを表しています。
「コチボユヌズ(雄羊の角)」は、力強さや豊かさの象徴。他にも、サソリ、ヘビ、鳥、木、星、輪のような形があり、それぞれに魔除け、幸運、命のつながりなどの意味があるとされています。
これらの模様は、地域や部族によって少しずつ形や意味が異なり、その土地の伝説や文化とも深く結びついています。キリムを見ることで、その背景にある物語を感じ取ることができるのです。
キリムは暮らしの中でどう使われてきた?
キリムは、昔から実にさまざまな使われ方をしてきました。床に敷くラグとしてだけでなく、テントの仕切り、荷物を包む布、袋や衣服としても使われてきました。
また、結婚式では花嫁が持っていく持参品として織られたり、お葬式では故人を包む布として使われたりもしました。キリムは人の一生の節目に寄り添い、大切な場面で役割を果たしてきたのです。
今では、ソファやベッドにかける布として、また壁に飾るアートとしても活用されています。実用性と装飾性を兼ね備えたアイテムとして、現代の暮らしでも高く評価されています。
キリムを長く楽しむためのお手入れ方法
キリムをきれいに保つには、日頃のお手入れが大切です。掃除機を使うときは吸引力を弱めて、表と裏の両方をやさしく掃除しましょう。フリンジ部分は引っかけないように注意が必要です。
ときどき屋外で軽くはたいてほこりを落とし、風通しの良い日陰で干すのもおすすめです。汚れた場合は、中性洗剤を薄めた水で手洗いし、しっかりすすいだ後に自然乾燥させましょう。直射日光や乾燥機は避けたほうが安心です。
長く使わないときは、清潔な状態で丸めて、通気性のある布に包んで保管します。湿気の少ない場所に置き、防虫剤は直接触れないように別の布にくるんで使いましょう。定期的に広げて風を通すことで、カビや虫を防ぐことができます。
現代の暮らしにもぴったりなキリムの魅力
最近では、キリムは北欧風やヴィンテージスタイルなどのインテリアにもよく合うと注目されています。特に手織りやアンティークのキリムは、部屋の雰囲気をぐっと引き立ててくれる存在です。
ネットショップや家具店、アンティークショップなどでさまざまなサイズやデザインが手に入ります。価格も幅広く、数千円の手頃なものから、数十万円する高級な一点物まであります。
また、自然素材や手仕事の価値が見直される中で、キリムは「サステナブル(持続可能)」なインテリアとしても人気です。大切に使えば、何十年にもわたって暮らしに寄り添ってくれるアイテムとなります。
まとめ キリムは心と文化をつなぐ織物
キリムは、単なる布ではなく、織った人の思い、地域の文化、家族の歴史が込められた特別な織物です。一つひとつの模様には意味があり、それを見る人に静かに語りかけてきます。
丁寧に作られたキリムを暮らしに取り入れることで、部屋に温かさや落ち着きを加えることができます。あなたも、自分だけの一枚を選んで、日常の中にちょっとした文化と物語を取り入れてみませんか?
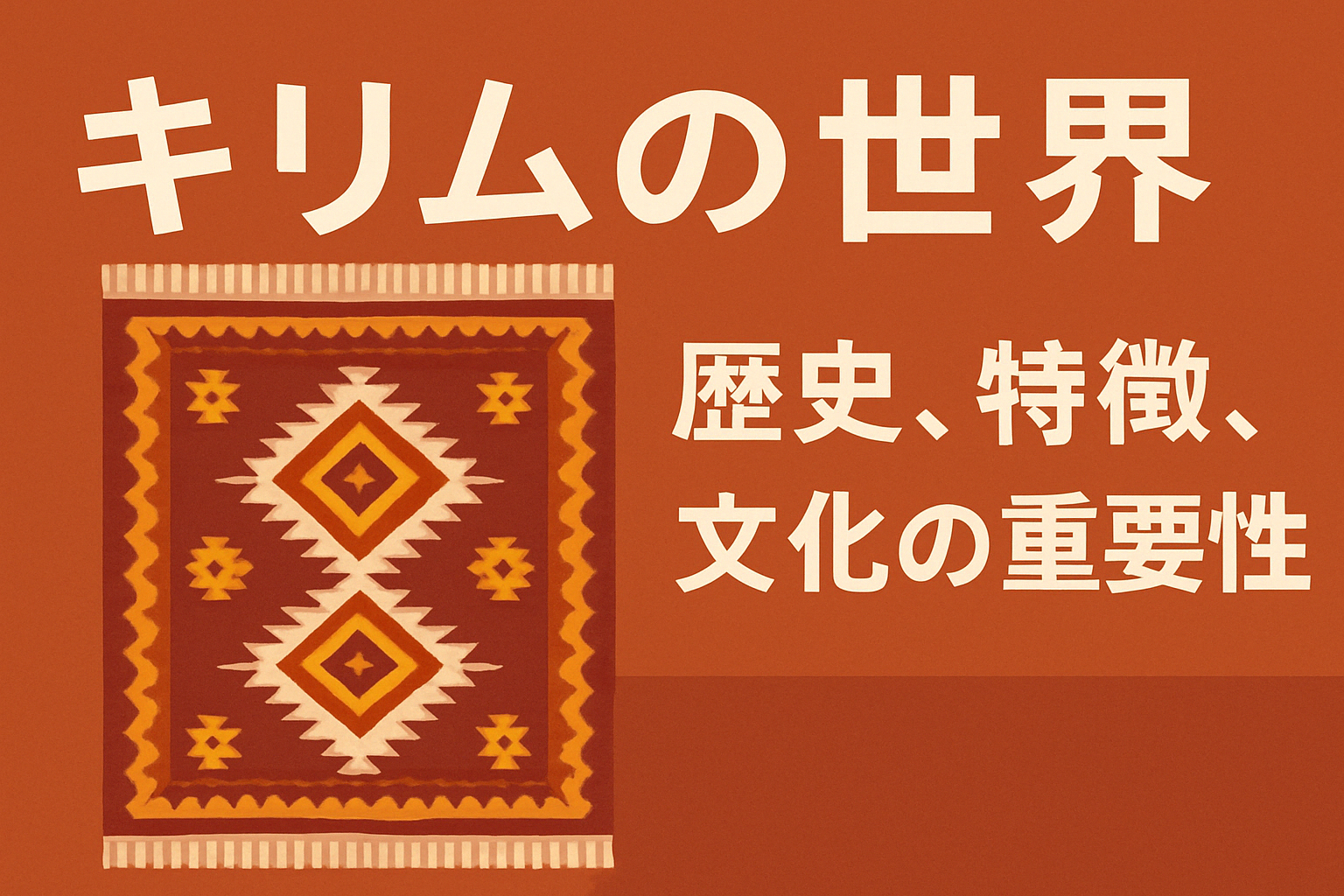

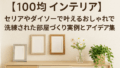
コメント